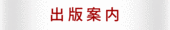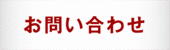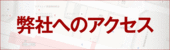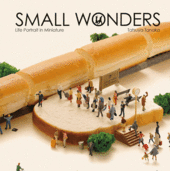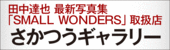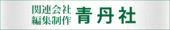内容説明
これはアートなのか?
世界的な美術ファンの拡大は、いまや“趨勢”である。
アートはエンタテイメント、教育、社会活動、医療や福祉にまで越境し、他の分野と結びつきを深めている。
しかし、〈芸術/アート〉とはなにか?「そもそもアートとは何なのか」という素朴で根本的な疑問や問いに対して、われわれは解を得ているだろうか?
社会とアートの関係の変化を共進化の過程として捉え「いかなる条件の下でモノ/行為は芸術作品になり、作り手はアーティストになるのか」という「転換の過程」に注目して、現代社会の文化現象を artification の視点で読み解く。特に文化芸術のもたらす(広義の)利益とそこに関わる利害関係者に注目し「転換の過程」すなわち「芸術の生成」の社会的論理を明らかにすることで、芸術にとっての社会、社会にとっての芸術の意味を探り、両者の望ましい関係のあり方とその未来の姿を展望する。
【編著者】
小松田儀貞(こまつだ・よしさだ)
秋田県立大学総合科学教育研究センター准教授。著書に『社会化するアート/アート化する社会』(水曜社)
【著者】
木村直弘(きむら・なおひろ)岩手大学人文社会科学部教授
野村幸弘(のむら・ゆきひろ)岐阜大学教育学部教授
阿部宏慈(あべ・こうじ)山形県立米沢栄養大学・米沢女子短期大学学長
笹島秀晃(ささじま・ひであき)大妻女子大学社会情報学部教授
戸舘正史(とだて・まさふみ)四国学院大学非常勤講師
*プロフィールは本書刊行時のものです。
世界的な美術ファンの拡大は、いまや“趨勢”である。
アートはエンタテイメント、教育、社会活動、医療や福祉にまで越境し、他の分野と結びつきを深めている。
しかし、〈芸術/アート〉とはなにか?「そもそもアートとは何なのか」という素朴で根本的な疑問や問いに対して、われわれは解を得ているだろうか?
社会とアートの関係の変化を共進化の過程として捉え「いかなる条件の下でモノ/行為は芸術作品になり、作り手はアーティストになるのか」という「転換の過程」に注目して、現代社会の文化現象を artification の視点で読み解く。特に文化芸術のもたらす(広義の)利益とそこに関わる利害関係者に注目し「転換の過程」すなわち「芸術の生成」の社会的論理を明らかにすることで、芸術にとっての社会、社会にとっての芸術の意味を探り、両者の望ましい関係のあり方とその未来の姿を展望する。
【編著者】
小松田儀貞(こまつだ・よしさだ)
秋田県立大学総合科学教育研究センター准教授。著書に『社会化するアート/アート化する社会』(水曜社)
【著者】
木村直弘(きむら・なおひろ)岩手大学人文社会科学部教授
野村幸弘(のむら・ゆきひろ)岐阜大学教育学部教授
阿部宏慈(あべ・こうじ)山形県立米沢栄養大学・米沢女子短期大学学長
笹島秀晃(ささじま・ひであき)大妻女子大学社会情報学部教授
戸舘正史(とだて・まさふみ)四国学院大学非常勤講師
*プロフィールは本書刊行時のものです。
目次
第1章 アートはいつ〈アート〉になるのか ―問題性としての〈アート化〉
第2章 批評家はなぜ批判されたか ―音楽批評と〈アート化〉
第3章 日本の美術はいつ〈アート化〉したか
第4章 映画祭と〈アート化〉の問題
―山形国際ドキュメンタリー映画祭の生成
第5章 路上で名付けられる側に回り続ける
―きむらとしろうじんじんの野点
第6章 アートと社会的実践の境界が滲むとき
―「アートでないアート」の可能性
第2章 批評家はなぜ批判されたか ―音楽批評と〈アート化〉
第3章 日本の美術はいつ〈アート化〉したか
第4章 映画祭と〈アート化〉の問題
―山形国際ドキュメンタリー映画祭の生成
第5章 路上で名付けられる側に回り続ける
―きむらとしろうじんじんの野点
第6章 アートと社会的実践の境界が滲むとき
―「アートでないアート」の可能性
関連書籍
関連記事
- 2026.2.2朝日新聞サンヤツ広告 - 2026.02.02
- 2025.11.27朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.11.28
- 2025.10.9朝日新聞サンヤツ広告 - 2025.10.09